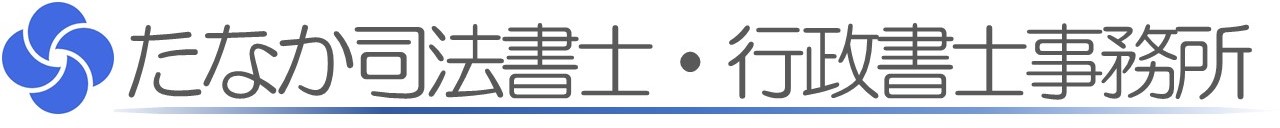目次
はじめに
「遺言はお年寄りが書くもの」というイメージを抱く方が多いかもしれません。
そして「遺言は実際に年をとったときに書けばいい」と考えてしまうかもしれません。
まだまだ年齢的には若い世代のときであっても、遺言書を書いていない場合は、どういった手続きを行わないといけないのでしょうか?
預貯金や株式の相続手続き、不動産の名義変更する場合に、相続人全員の「実印」が押印された遺産分割協議書の作成が必要になります。
相続人の中に、1人でも反対する人がいると相続手続きは何も進めることができなくなります。家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することとなり、多くの時間と費用がかかるだけでなく、預金や不動産が凍結されてしまい、生活費や納税資金の準備にも支障が出ることがあります。
遺言を作成することをおすすめする場合
夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合、法定相続人は、残された配偶者と亡くなった夫(妻)の父母です。夫(妻)の父母が既に亡くなっているときは、残された配偶者と夫(妻)の兄弟姉妹が法定相続人となります。
つまり、遺言が無ければ、残された配偶者は自分にとって義理の父母または義理の兄弟姉妹と遺産分割協議を行う必要があります。
夫(妻)の親戚と普段から交流がないときに、遺産分割協議の話を進めにくいことが考えられます。遺産分割協議が難航する事が想像できますし、大変な労力を伴うでしょう。
このような場合は、遺言を書いておくことによって、残された配偶者を遺産分割から守ることができます。
夫婦の間に未成年の子供がいる場合
夫婦の間に未成年の子供がいる場合、法定相続人は、残された配偶者と子供になります。
子供が未成年の場合、未成年の子供と妻が遺産分割協議を行うためには、「特別代理人」を選任する必要があります。未成年の子供が複数いる場合、その子供の人数分、特別代理人は必要になります。
特別代理人の選任は管轄の家庭裁判所に申立書を提出して、家庭裁判所に選任してもらいます。
特別代理人の候補者は、相続人との利害関係のない人でなければなりません。相続人との間に利害関係のない人であれば、親族であっても記載することができます。この場合、親族(子供の祖父母や叔父叔母)を特別代理人の候補者として記載すれば、選任されるのが通常だと思われます。
また選任申し立ての段階で遺産分割協議書案の提出が求められます。原則として、その内容が未成年者に不利なものである場合は特別代理人の選任が認められないのが通常であるため、「法定相続分」による相続である必要があります。
このような場合は、遺言を書いておくことによって、上記の手続きを経ることなく、残された配偶者に相続させることができます。
内縁関係や同性婚の場合
内縁関係や同性婚のパートナーは、現在の民法では法律上の夫婦ではないため、相手方が一方的に関係を解消した場合にも,離婚の場合と同様に財産分与や慰謝料請求が認められることがありますが、相続権についてはまだ認められていません。
大切なパートナーに財産を残すためには、遺言を書いておくことが必要になります。
離婚歴があり、前妻(前夫)との間に子供がいる場合
例えば先妻との間に子供がおり、そして、後妻との間にも子供がいる場合、夫が亡くなったときは、法定相続人は、現在の妻とその子供及び先妻との間の子供になります。
夫が円満に離婚しており、先妻側との関係が良好であれば問題はありません。しかし、先妻側との関係が悪いときや、現在の子供たちはその存在さえ知らないこともあるでしょう。そうなると出会ったこともない腹違いの兄弟姉妹と遺産分割協議をしなくてはなりません。
先妻側との遺産分割協議が難航する事が想像できますし、大変な労力を伴うでしょう。そして、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することとなった場合には、多くの時間と費用がかかるだけでなく、預金や不動産が凍結されてしまい、生活にも支障が出ることがあります。
遺産争いとならないためにも、遺留分に配慮した遺言を書いておくことが必要になります。
※遺留分とは、遺言によってもなくすことができない相続権の割合のことです。
相続人の中に認知症の方や行方不明者の方がいる場合
相続人の中に認知症の方で、判断能力がなく意思表示ができない方がいる場合には、そのままでは遺産分割の話し合いができません。また相続人の中に行方不明者の方がいる場合も同様に、その方以外の相続人の間でなされた遺産分割の話し合いは、無効となります。
遺産分割協議を行うためには、家庭裁判所において認知症の方の成年後見人を選任してもらう必要があります。さらに相続人のうちの1人が成年後見人になった場合は、特別代理人を選任しなければなりません。誰を選任するかは、最終的には裁判所が判断することになります。必ずしも申立書に記載した後見人候補者が選ばれるとは限りません。
また家庭裁判所において行方不明者の方の不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。親族内から不在者財産管理人を選任したい場合は、相続人でない親族であることが大前提となります。
この場合、相続手続きがすべて終わるのに多くの時間と費用がかかります。
遺産分割ができないために相続手続きを進めることができなくならないためにも、遺言書を書いておくことおくことが必要になります。
未婚や独身の場合
未婚や独身の方が亡くなったとき場合、法定相続人は、その方の両親です。両親が既に亡くなっているときは、兄弟姉妹となります。さらに兄弟姉妹も亡くなっているときは、甥・姪が法定相続人となります。
兄弟姉妹と普段から交流があり、関係が良好であれば、生前に相続等について話し合いができますが、普段から疎遠な場合、兄弟姉妹または甥・姪の間で、争いが起こることも予想されます。
お世話になった友人や知人などに遺贈したり、支援したい団体に寄付するなどの内容の遺言を書いておくこともできます。また、兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺言を書いておけば、財産を自由にご自身の希望する人や団体へ渡すことができます。
会社経営者の場合
会社経営者の場合、事業をどうするかについて検討する必要があります。事業を継続させるのか解散するのか、事業を継続させるのならば、後継者をどうするのかです。
会社の株式は、法定相続分に応じて引き継がれてしまうと、事業の継続に支障が出ることが考えられます。後継者が過半数の株式を保有する事となるような、遺言を書く必要があります。
さらに加えて、会社の経営をめぐり相続人間で争いなどが起こってしまうことは、会社の経営・財務基盤を弱体化させることになりかねない大きな問題です。後継者以外の相続人には、遺留分に配慮し、他の財産を相続させるような、遺言を書く必要があります。
最後に
「遺言はお年寄りが書くもの」と思わず、上記の事例に1つでも当てはまる方は、遺言書を書いておくことをおすすめします。
なお、実際に遺言を作成する場合は、財産やご家族の状況等、考慮すべきポイントがあります。
また、遺言を作成しても「遺留分」の問題はどうしても発生します。遺留分とは、遺言によってもなくすことができない相続権の割合のことです。
それでも遺留分に配慮した遺言や付言事項に理由や思いを書く等の対策を行うことで、遺言を残さなかった場合によるトラブルを避けることができます。
自筆証書遺言のように法律の要件を満たさないために無効となることと比較し、公正証書遺言は、遺言の中で最も高い確立で執行してもらえるものなので、遺言をお考えの方には、公正証書遺言をおすすめしています。
遺言書案の作成から公証役場との事前打ち合わせまでの手続き、また証人の手配についても、ぜひお気軽に司法書士にご相談ください。
TEL 0855-52-7183
(平日8:30~17:15)
お電話の場合、移動中や打合せ中のときは留守番電話に切り替わります。予めご了承ください。

最終更新日 2020年8月19日